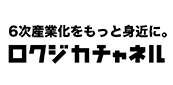商品ブランディングでありがちな失敗例とは?
2018/02/07

専門家ならではの鋭い視点で、生産者を導いてくれ る6次産業化プランナー。数ある案件に携わってきた人気プランナーたちのこぼれ話をご紹介。第2回は、商品作りでよくある悩みについて。
case.1 商品の差別化が図れず、結局安い値段で売ってしまう
「味と品質には自信があるけれど、売れない、目立たない」という生産者の方の声をよく聞きます。例えば、りんごやぶどうなどをジュースに加工・販売したとします。でも同じことを考える人たちは一定数存在していますから、お店に並んだとき、他の商品に埋もれてしまうのです。そのため、結局は価格競争に巻き込まれ、安い値段で販売せざるを得なくなり、儲けを生み出せなくなるということも……。そうならないためには、ジュースの商品自体や売り方、パッケージなどに個性を与えてブランディングし、差別化することが重要です。大手メーカーの大量生産品と同じことをしていてもダメなのです。

case.2 コンセプトがあいまいでイベントで「売って終わり」に
生産者自身ができること、やりたいことが明確になっておらず、あいまいな状態で製造・販売を始めてしまうことがあります。商品のコンセプトによって、消費者のターゲット層、売る場所、生産量などが変わりますので、たとえば「高品質で生産量が少ないため、高級路線にしよう」「高級路線のなかでも、ワインのおつまみなどおしゃれなイメージにしよう」など、方向性をはっきりさせるのが先決です。やみくもにイベントに出店しても、訪れる人たちと商品が噛み合わず「その場で売って終わり」になってしまいがちです。まずは消費者に伝えるべき部分を生産者自身がしっかり決めること。それに合わせてロゴやパッケージ、あるいは生産者自身などをブランディングしていきましょう。

case.3 6次産業化そのものの進め方が分からない
6次産業化に挑戦したいと思っても、何から手をつけていいのか分からない人も多いようです。農産物からどうやって商品化するのかなど、一連の流れが掴めずに諦めてしまう人もいます。また、商品は作ったけれども、輸送の知識がない、ブランディングができていないという場合も。1人で考えてばかりではなかなか先に進みませんし、6次産業化には各専門家の知識がとても役立ちます。まずは各都道府県の6次産業化サポートセンターに相談するのもひとつです。継続していくためにも、製造から販売までトータルでコントロールできる状態を作ることが大切です。

取材協力
長岡淳一 さん
1976年生まれ。株式会社ファームステッド代表取締役、6次産業化プランナー。地域振興クリエイティブディレクターとして、日本各地の農業のブランディングを手がける。過去には観光庁目利きアドバイザーも歴任。
ロクジカチャネルvol.20 より転載